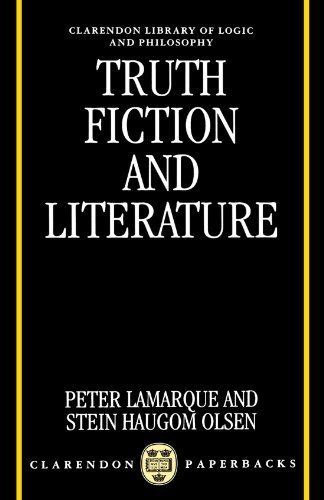まえおき
ノエル・キャロル『ホラーの哲学』の翻訳が出ます。出版社の告知ページも出たので宣伝していきます。
たまたまタイミングが合って、ユリイカ2022年9月号 特集=Jホラーの現在にも書いています。
このふたつの仕事が重なったため、すっかりホラーづいており、毎日何がしかのホラー映画、ホラー小説を摂取している夏です。
翻訳出版に合わせて『ホラーの哲学』の宣伝をしていきたいと思います。
紹介
まずは目次。章タイトルなどはまだ仮です。
目次(仮)
- 序
- 本書が置かれた文脈
- ホラージャンル摘要
- ホラーの哲学とは?
- 第一章 ホラーの本質
- ホラーの定義
- まえおき
- 感情の構造について
- アートホラーを定義する
- アートホラーの定義に対するさらなる反論と反例
- 幻想の生物学とホラーイメージの構造
- 要約と結論
- ホラーの定義
- 第二章 形而上学とホラー あるいはフィクションとの関わり
- 第三章 ホラーのプロット
- ホラープロットのいくつかの特徴
- 複合的発見型プロット
- バリエーション
- 越境者型プロットおよびその他の組み合わせ
- 典型的ホラー物語が与えるもの
- ホラーとサスペンス
- 疑問による物語法
- サスペンスの構造
- 幻想
- ホラープロットのいくつかの特徴
- 第四章 なぜホラーを求めるのか?
まじめに紹介しようと思うと大変なのでハードルを下げるために、断片的に紹介していきます。つづくかはわかりませんがなるべくがんばります。
少し前に出た戸田山和久『恐怖の哲学』でも紹介があったので、おそらく本書では最終章のホラーのパラドックスの話が有名だと思います。ホラーのパラドックスというのは、なぜ怖いのに見るのか、普通怖いものは避けるはずなのにどうしてわたしたちはホラーを求めるのかという問題です。
これはこれでおもしろいんですが、ただ、個人的には、ホラーのパラドックスの話ばかりが言及されるのはあまりおもしろくない、本書には他にもおもしろい部分がたくさんありますよという風に思っています。
そういうわけでちょっとずつ紹介していきます。
今日紹介したいのは、一章後半の「幻想の生物学とホラーイメージの構造」の節。怖いモンスターの作り方を分析した箇所です。ここは「カテゴリーを組み合わせて君だけのホラーモンスターを作ろう」みたいな最高に楽しい箇所ですね。キャロルはここで「融合」「分裂」「巨大化」「群集化」という四つのメソッドを紹介しています。
キャロルの意見によれば、ホラーをかきたてるものというのは、カテゴリー的にどこに位置づけて良いのかよくわからない「不浄なもの」「狭間に位置するもの」です*1。この四つのメソッドは、不浄性を作り出したり、強めたりする手法として紹介されます。
融合というのは、人間に馬の頭がついてるとか、そういうやつです。かけ離れた複数のカテゴリーをくっつけるといいですね。
分裂は、時間分裂と空間分裂があるんですが、時間分裂の代表例は人間が狼になるとかです。空間分裂の代表例はドッペルゲンガーです。
巨大化は、文字通り巨大化で、群集化は群れを作るやつです。
巨大化・群集化は、不浄を作るというより強める方なので、元々キモいものを巨大化させたり、群集化させるのが効果的であると薦められています。
正直この辺の手法って、古典的なモンスターホラーではよく見たけど、最近はあまり見ないですね。少し前にネット怪談に題材をとった『犬鳴村』という映画があり、犬鳴村って別に元々はそういう話ではないと思うんですが、映画だとそういう話になってて、個人的には結構好きでした。古典的なモンスター映画が好きなので。
ただ、人間に豚の頭とか犬の頭がついてるやつはシンプルに怖いですからね。現在でも別に無しではないと思います。
本書に出てくるホラー作品の紹介コーナー
以前から個人的に考えていた企画として、本書に出てくるホラー映画、ホラー小説を適当に紹介していくというのがありました。『エクソシスト』とかそういう有名なのもいいんですが、変なやつ中心に。あんまり需要ないと思うんですが、無理矢理解説にくっつけていきます。
栄えある第一回はネイサン・ジュラン監督の『極地からの怪物 大カマキリの脅威』(1957)です。配信とかは無いと思うのでDVDを探してください。2千円くらいで買えます。
ちなみに本作は、どこで出てくるかと言うと、今回紹介したモンスターの作り方の例で出てきます。タイトルを見ればわかるように巨大化のめっちゃわかりやすい例です。極地の氷の中で眠っていた巨大カマキリが復活します。実は50年代にこの手の動物巨大化ものってすごくたくさん作られていて、わたしは個人的にこのジャンルがめっちゃ好きです。
本作が今でも観る価値がある作品かというと微妙なんですが、どういう人におすすめなのかははっきりしています。怪獣映画ファンです。特に初代『ゴジラ』とか、『サンダ対ガイラ』とか昭和の最初の頃のおどろおどろしいやつが好きな人にはおすすめです。怪獣映画として観ると、軍隊と巨大カマキリの対決とか見どころもあってそんなに悪くないです。
これは最初の展開がすごく良くて、最初の場面で「アメリカが誇る最先端のレーダー網!」みたいな感じで、米軍のレーダー網の素晴しさが強調されるんですよね。そのレーダー網に謎の高速飛行物体が検知される、だが、その正体は……という(わかると思いますが、もちろん巨大カマキリです)。ちなみに巨大生物がレーダーにひっかかる場面は、日本の『空の大怪獣 ラドン』(1956)にもあって、この映画が1957年なので、おそらくこの映画が『ラドン』をぱくってますね。
個人的に怪獣映画の魅力って、怪獣というふざけたものが、国家、軍隊、科学というまじめなものと衝突するところにあると思っていて、軍のレーダー網が巨大カマキリに反応するのは、この衝突が感じられて好きですね。
*1:正確に言うと、危険でコワイ、かつ、不浄でキモイという二条件があるんですが、危険でコワイ方は当たり前なのであまり強調されません。

![極地からの怪物 大カマキリの脅威 [DVD] 極地からの怪物 大カマキリの脅威 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51a9SM68dqL._SL500_.jpg)